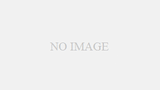「妊活しているのに子供ができない…」「もしかして不妊症?」と悩んでいませんか?
子供ができないのは、自覚していないだけで病気が原因になっていることもあります。また、女性側だけでなく、男性側に原因があることも。
まずは子供ができない原因を突き止めることで、妊活も上手く進むようになります。
ここでは子供ができない原因を男女別にご紹介。検査方法も詳しく解説していきます。さらに子供ができやすい体を作る方法も併せてお伝え!
こちらの記事を読んで子供ができない原因を突き止めると共に、子供ができやすい体づくりをはじめましょう!
記事まとめ
・子供ができない原因を知るには?…男性・女性ともに不妊検査で原因を確かめられる!
・女性不妊の症状はある?…月経周期の乱れや過度な月経痛には注意!ピルでの改善に期待!
・不妊を予防するには?…ピルの服用がおすすめ!原因となる子宮内膜症や月経不順の予防に!
子供ができない「不妊症」の定義とは?
なかなか子供ができない場合には、「もしかしたら私って不妊症なのでは?」という不安がよぎります。
そこでまずは「不妊症」とは、どういう状態なのかを詳しく見ていきましょう。不妊は以下のように定義されています。
日本産科婦人科学会では、この「一定期間」について「1年というのが一般的である」と定義しています。」
現在妊活をしていて、妊活開始から1年以上経過している場合には「不妊」にあたるということです。
ただし、この定義に当てはまらない場合でも「不妊なのでは?」と感じる場合は、なるべく早めに検査を受けてみるのがおすすめです。
【年齢・男女別】子供ができない確率一覧
妊活を始め、避妊せずに性行為を行うと、1年後には90%の確率で妊娠すると言われています。よって、不妊の定義に当てはめると、10組中1組は不妊であることになります。
また、不妊になる確率は年齢によっても異なります。女性の年齢ごとに、1年以内に子供ができない確率を見ていきましょう。
| 女性の年齢 | 20代前半 | 20代後半 | 30代前半 | 30台後半 |
| 1年以内に子供ができない確率 | 3% | 7~14% | 28% | 35% |
上記の表を見てみると、年齢を重ねるほど不妊率が高くなることがわかります。また、女性だけでなく男性も年齢が高くなるほど、子供ができなくなる確率は上昇します。
「不妊かもしれない…」と感じながら原因を突き止めず、検査を先送りしていると自然妊娠する確率も下がる一方。なるべく早く検査を行い、病気が原因であれば早期治療を行いましょう。
子供ができない原因の割合は男女どちらが多い?
子供ができない原因は、女性側にあると思われがち。実際に「自分に原因があるのでは?」と思っている方も少なくありません。
男女別に不妊症の原因がある確率はWHOの調べによると、下記の通り。
| 女性側 | 男性側 | 女性・男性両方 |
| 41% | 24% | 24% |
女性側でなく男性側に原因があることも考えられます。検査を行う場合は、まずは自分だけ受けてみるのも良いですが、夫婦揃って検査を受けることをおすすめします。
子供ができない原因について検査前に知りたいQ&A3つ
子供ができない場合は、なるべく早く検査を受ける必要があるとわかりましたが、検査前には不安や疑問点も出てきます。
ここからは子供ができない原因を調べるための検査へ向かう前の、よくある質問にお答えしていきます。
「検査を受けても病気が見つからないケース」があるのか。また、「低用量ピルによる不妊への影響」や「家系(遺伝)が関係するのか」を解説していきます。
1. 病気による原因がなくても子供ができないことはある?
子供ができない原因は病気である可能性があるとお伝えしましたが、必ず病気であるとも限りません。
中には検査を行っても原因が見つからず、原因不明とされる場合もあります。その割合は不妊症の10~15%。
高年齢で不妊に悩む女性が増加してきたため、原因不明の割合は年々増えてきています。加齢による不妊とならないよう、早めの不妊治療や不妊予防策を行うことが大切です。
2. 低用量ピルを飲み続けると子供ができない原因になる?
ピルは2種類のホルモンを含んでいるので、服用することで女性ホルモンの働きを助ける役割があります。毎日1錠ずつホルモンの配合量が調整されたピルを飲むことで、生理周期を正常に導きます。服用による赤ちゃんへの影響も特に問題ありません。
不妊症の予防や妊活に向けての準備として、低用量ピルの服用はおすすめです。自宅にいながらピルの処方を受けられるので、気になる方は利用してみてください。
3. 子供ができない原因に家系(遺伝)は関係する?
親族の中に不妊症の方がいると耳にした経験がある方は、子供ができない原因を家系(遺伝)だと考えてしまいがちです。
しかし、子供ができない原因は、病気以外にも生活習慣などが大きく関わっています。よって、子供ができない原因が家系にあるとは言い切れません。
また、不妊の原因で遺伝する可能性があるのは「無精子症」です。男性の不妊症の原因の10%が無精子症とされています。
無精子症かどうかは、「【男性】子供ができない原因や病気がわかる検査方法4選」でご紹介する精液検査で確認が可能です。身内に無精子症の方がいるなどの不安があれば、精液検査を受けてみましょう。
【女性】病気の可能性もある子供ができない原因5つ
子供ができない場合、女性側にはどのような原因が考えられるのか、お伝えしていきます。
まず女性側の子供ができない原因として考えられるのは、主に5つあります!
子供ができない原因
1.排卵因子…うまく排卵されない
2.卵管因子…卵管周囲の閉塞や周囲の癒着
3.子宮因子…受精卵が着床できない
4.頸管因子…子宮頸管を精子が通れない
5.免疫因子…免疫異常によって精子を妨げる
ここからは子供ができない各原因について、詳しく解説していきます。症状が出るものに関しては、その特徴を掲載していますので、心当たりがないか併せてチェックしていきましょう。
1. 排卵因子が原因|うまく排卵がされない
通常、排卵が起こると女性ホルモンの分泌に変化が起き、子宮は妊娠に向けての準備段階に。そして卵子と精子が受精すると、準備された子宮へ着床し妊娠に至ります。
しかし、排卵障害が起こると、通常月経の約14日後に起こる排卵がない状態に。また、排卵されるまでに異常が起こり、卵が育たなかったり、育っていてもうまく排卵できなかったりします。
| 排卵障害になる原因 | ・女性ホルモンに影響する病気 ・ホルモンのバランス異常(多嚢胞性卵巣症候群) ・卵巣機能の低下 ・肥満や極度のダイエット ・精神的なストレス など |
| 症状 | 月経不順が続く |
| 治療法 | 排卵誘発剤の使用など |
| 検査方法 | 基礎体温測定 |
排卵障害の症状としては、月経不順が続いている方が多くいます。また、排卵障害かどうか確かめる方法としては、基礎体温の測定がおすすめ。
もし排卵障害と診断された場合の治療法は、原因に合わせて排卵誘発剤(卵子を発育させ排卵を促す薬)の使用などが行われます。排卵誘発剤を使用する排卵誘発法には、内服と注射の2通りの方法があります。
また、生理不順で悩んでいる方は、低用量ピルの服用で改善が期待できます。低用量ピルは周期に合わせたホルモンが配合されており、月経周期を安定させると共に、服用中に排卵を抑制します。生理周期が整うと、ピル中止後には排卵も起こりやすくなると言われています。
生理不順の方は低用量ピルの服用で、生理周期を安定させることから始めてみるのもおすすめ。ピルをオンラインで購入できるので、気軽にスタートさせてみてください。
2. 卵管因子が原因|卵管の閉塞や卵管周囲が癒着する
通常精子は卵管を通り卵子に向かい、受精を行うと再び卵管を通り子宮へ戻っていきます。そして、子宮へ戻った受精卵が着床し妊娠に至ります。
しかし、卵管が詰まってしまっていたり(閉塞)、卵管の周囲が癒着していたりといった異常があると、精子や卵子の通り道がなくなり、不妊の原因となります。
| 卵管に問題がある場合の原因 | ・子宮内膜症 ・腹膜炎の既往 ・クラミジア感染症 ・虫垂炎など骨盤内手術 など |
| 症状 | 強い月経痛 |
| 治療法 | ・非観血的卵管再疎通術 ・腹腔鏡手術 |
| 検査方法 | ・クラミジア抗体検査 ・卵管疎通性検査 ・腹腔鏡検査 ・子宮鏡検査 など |
卵管の閉塞や卵管周囲の癒着が起こりやすい子宮内膜症の症状としては、強い月経痛があります。「月経時は鎮痛剤が欠かせない!」という方は、子宮内膜症の疑いがあります。
また、卵管の異常や子宮内膜症かどうかを確認するには、病院での検査が必要です。
卵管の閉塞や卵管周囲の癒着が見られた場合は、詰まりや癒着箇所に合わせ手術療法を行います。
・腹腔鏡手術…腹腔鏡をみながら癒着を剥離する方法
もし子宮内膜症の疑いがある場合には、低用量ピルの服用もおすすめです。低用量ピルは排卵を抑制して、妊娠している状態に近くなることで、子宮内膜の増殖を抑える作用と共に、月経痛の軽減にも期待が持てます。
月経痛がひどくて悩んでいる方は、オンラインで医師の診察や相談を受けられる「低用量ピルオンライン」をチェックしてみてください。
3. 子宮因子が原因|子宮内膜へ受精卵が着床できない
精子と卵子は受精すると、卵管を通り子宮へと戻っていきます。そして子宮内に戻った受精卵は、子宮内膜に着床し育っていきます。
しかし、子宮内膜の異常増殖や血流不良、過去の手術の影響で炎症や癒着が起こっていると着床が妨げられ不妊の原因となります。
| 着床障害の原因 | ・子宮筋腫(粘膜下筋腫) ・子宮腺筋症(子宮内膜症の一種) ・子宮内膜ポリープ ・子宮の形に異常のある場合 など |
| 症状 | 月経痛・過多月経 |
| 治療法 | 手術・投薬 |
| 検査方法 | MRI検査 |
子宮筋腫は、30歳以上の女性だと20~30%の確率で認められます。その中でも、子宮の内側まで発育してしまっている粘膜下筋腫の割合は15~25%。症状としては、月経痛や過多月経などがあります。
また、子宮内膜ポリープがある場合、不正出血が起こる可能性もありますが、無症状の場合もあります。子宮因子がないか確認する際には、MRI検査を行うのがおすすめです。
子宮因子が見つかった時は、病気に合わせ手術や薬での治療が行われます。子宮内膜ポリープの治療であれば、ポリープを摘出することになっても日帰り手術で済む場合もあります。
4. 頸管因子が原因|子宮頸管を精子が通れない
子宮頸管は膣と子宮を繋ぐ、子宮の入口にあたる部分です。通常排卵が近づくと精子が通りやすい状態へと変化し、子宮内へ精子を迎え入れ受精します。
しかし、子宮頸管に異常があると、頸管の内部を満たす粘液量が少なくなり、精子が通りにくくなります。精子が子宮内にたどり着けないと、妊娠が起こりづらく不妊の原因になるのです。
| 頸管に問題がある場合の原因 | ・頸管粘液不全 ・子宮頸部の炎症 ・子宮頸部の手術 など |
| 症状 | 排卵時のおりものの減少 |
| 治療法 | 卵胞ホルモンによる薬物療法 |
| 検査方法 | フーナーテスト |
頸管粘液不全は、排卵誘発剤であるクエン酸クロミフェン(クロミッド)という薬を長期服用した副作用で起こるケースがあります。
排卵時期におりものが少ないと感じる場合は、子宮頸管の検査を受けてみましょう。
もし頸管粘膜不全が見受けられた時には、卵胞ホルモンによる薬物療法で治療が進められます。
5. 免疫因子が原因|免疫異常によって精子を妨げる
人は元々「免疫」を持っていますが免疫異常により、頸管粘液や精子の状態に問題があることがあります。
免疫は本来、細菌やウイルスから守るためのシステムです。しかし、免疫異常が起こると、精子を異物と判断して子宮への侵入を防いでしまうことがあります。
| 免疫に問題がある原因 | ・抗精子抗体 ・精子不動化抗体 |
| 症状 | ー |
| 治療法 | 人工授精又は体外受精 |
| 検査方法 | フーナーテスト |
「抗精子抗体」とは精子を攻撃してしまう抗体、「精子不動化抗体」は精子の運動を止めてしまう抗体のことです。
抗精子抗体や精子不動化抗体を持っている確率は、不妊症の女性の約3%。抗体を持っているかは、フーナーテスト(性交後検査)、採血検査で確認します。
抗精子抗体が見受けられた場合、この抗体を無くすことはできません。
治療法としては、抗体値によって人工授精又は体外受精(顕微授精)を行っていきます。
不妊の原因がどこにあるのかは、どのケースでも早期発見が大切です。原因がわかれば、さまざまな治療法があるので、まずは早急に病院での検査を受けるようにしましょう。
【女性】子供ができない原因や病気がわかる検査の進め方
子供ができない原因を知るためには、まず病院へ行き診察と検査を受ける必要があります。どのように検査を進めていくのかを確認していきましょう。
不妊検査の対象は、健康な男女が避妊なしで性交を行っているのに、1年以上妊娠しない場合が主になります。ただし少しでも不安があるなら、妊活1年以内であっても早めの受診がおすすめです。
まず女性が行う不妊の基本的な検査(一般検査)をお伝えしていきます。
基本的な検査
・基礎体温測定
・超音波検査
・内分泌検査
・クラミジア抗体検査
・卵管疎通性検査
・フーナーテスト(性交後検査)
上記の検査で原因がわからなかった場合や、卵管・子宮の精密な検査が必要になった場合には、特殊検査を受けます。
特殊検査
・腹腔鏡検査
・子宮鏡検査
・MRI検査
検査によって、いつでも受けられるものもあれば、適切な時期が定められているものも!各検査の細かい流れは、病院で診察後に医師と相談して計画を立てます。
【女性】子供ができない原因や病気がわかる検査方法9選
子供ができない原因を知るための検査には、さまざまな方法があります。特に女性は、婦人科での検査を「恥ずかしい…」「どんなことをされるか不安…」と感じます。
そこで各不妊検査の内容を詳しくお伝えしていきます。どのような流れで検査が行われて、どんな原因が突き止められるのかを確認しましょう。
基本的な検査(一般検査)に加え、特殊検査についても掲載していますので、チェックしてみてください。
1. 基礎体温測定をする|排卵因子がないか調べる
基礎体温測定は、病院ではなく自分自身で行います。小数点第2位まで測定可能な「婦人体温計」を使用しましょう。
毎日目が覚めたらすぐ(体を起こす前)に舌の裏側で体温を測定します。測定した基礎体温は、基礎体温表に記載しましょう。
| 確認できる原因・病気 | ・排卵の有無 ・黄体機能不全の有無 ・不正出血の原因 |
| 検査に適した時期 | 毎日(1ヶ月以上) |
基礎体温は通常、生理開始から約2週間ほど低い体温(低温期)が続き、排卵が起こると上昇し約2週間高い体温(高温期)が続きます。
体温の上昇が見られない場合や基礎体温がバラバラだと、排卵因子の疑いがあるということ。
基礎体温の測定は病院に行く前からできますので、早速基礎体温を測定する習慣をつけていきましょう。
2. 超音波検査を行う|排卵因子や卵管因子であるかチェック
超音波検査は、診察室の診察台の上で行う検査です。超音波を発する器具(プローブ)をお腹の上に当てていきます。
膣内からの経腟超音波(経腟エコー)は、膣内に器具(プローブ)を挿入していき、モニターで画像を確認しながら検査を行います。
| 確認できる原因・病気 | ・子宮の肥大、変形の有無 ・子宮がん ・子宮筋腫 ・子宮内膜症 ・子宮腺筋症 ・卵巣がん ・卵巣のう腫 ・子宮内膜ポリープ など |
| 検査に適した時期 | 確認箇所によって異なる |
不妊治療では、超音波検査での子宮と卵巣の観察は必須です。子宮・卵巣の観察を行うことで、排卵因子や卵管因子がないかを確認できます。
超音波検査は婦人科を受診した際に、経験したことがある方の多い検査です。検査は数分~10分程度で終了します。
経腟超音波に使用する器具(プローブ)は細い棒状のものなので、性交経験があれば基本的に痛みや出血の心配もありません。
3. フーナーテスト(性交後検査)をする|頸管因子・免疫因子ではないか調査
フーナーテスト(性交後検査)は、頚管粘液(頸管の内部を満たす粘液)が充分に分泌されている排卵時期に性交を行います。そして性交を行った後に来院し、頸管因子がないか確認します。
来院後は子宮内から頸管粘液を採取し、子宮頸管内・子宮腔内の精子の数や運動量を調べます。
| 確認できる原因・病気 | ・抗精子抗体 ・乏精子症(男性因子) ・精子無力症(男性因子) |
| 検査に適した時期 | 排卵時期 |
「フーナーテストで精子の動きが悪い」「精子の動きが確認できない」場合には、抗精子抗体検査を行い免疫因子がないか確認します。
抗精子抗体検査は採血で行い、血液中の抗体確認と抗体の強さを測定していきます。
性交のタイミングは医師から指示があります。男性側の協力も必要ですので、パートナーと相談した上で検査に望みましょう。
4. 内分泌性検査をする|排卵因子か確認する
内分泌検査は採血を行い、採取した血液中の各ホルモン検査を行います。女性ホルモン・男性ホルモン、黄体ホルモン、甲状腺ホルモンなど。
さまざまなホルモンが妊娠に関わっており、各ホルモンの分泌量などを調べることで排卵因子の確認などを行うことができます。
| 確認できる原因・病気 | ・子宮の機能不全 ・卵巣の機能不全 ・排卵障害 ・甲状腺の病気 など |
| 検査に適した時期 | 月経期・黄体期 |
ホルモン量は月経周期によって変化していくので、1回だけではなく月経期と黄体期に分けて検査を行います。
各ホルモンの検査に適した時期
・月経3日目…黄体化ホルモン、卵胞刺激ホルモン、卵胞ホルモン
・排卵1週間後…黄体ホルモン
各ホルモン検査に適した採血日は医師から指示がありますので、日程を調節し指定された日の受診を行いましょう。
5. クラミジア抗体検査をする|卵管因子であるか調べる
クラミジア抗体検査は、血液を採取しクラミジア抗体を調べます。クラミジア抗体検査では、過去にクラミジアに感染したことがあるかを確認。
子宮頸管に感染しているかどうかを調べる場合は、子宮頸管内の細胞を擦りとってクラミジア抗原検査を行います。
| 確認できる原因・病気 | ・卵巣の病変の有無 ・卵管性不妊(卵管通過障害) |
| 検査に適した時期 | いつでも |
クラミジア抗体が陽性だった場合でも、全ての方に卵管因子があるとは限りません。陽性だった場合には子宮卵管造影(HSG)を行い、卵管の通過性や癒着を確認し判断していきます。
子宮卵管造影は子宮口から管を入れ造影剤を流し、子宮内の状態や卵管の通りなどを確認する検査です。
クラミジア感染症は、妊娠した際に流産や出産時の産道感染を起こすこともあります。早期発見を心がけましょう。
6. 卵管疎通性検査で確認|卵管因子によるものか確認する
卵管疎通性検査には3つの種類があります。
・子宮卵管造営法・・・造影剤を流しX線で卵管の通りを確認。
・卵管通気法・・・子宮口から炭酸ガスを注入して聴診器や装置を用いて数値(卵管通気曲線)で確認する。
・超音波下卵管通水法・・・気泡を含んだ溶液を流し超音波で確認を行います。
3種類の検査は全て行うのではなく、必要に応じ検査方法が選択されます。検査によっては痛みを伴うものもありますので、医師と相談しながら適切な検査方法を選んでいきましょう。
| 確認できる原因・病気 | ・卵管の閉塞や狭窄 ・卵管留水症 ・卵管周囲の癒着 ・子宮奇形 ・子宮筋腫 など |
| 検査に適した時期 | 月経終了から排卵前まで |
卵管疎通性検査はどの検査も月経終了から排卵日数日前、妊娠の可能性がない低温期に行います。
7. 腹腔鏡検査・子宮鏡検査の実施|卵管因子がないか調べる
腹腔鏡検査と子宮鏡検査はここまでご紹介した基本検査に加え、さらに卵管因子と子宮因子を調べる必要がある場合に行われます。
・子宮鏡検査・・・子宮口から細いカメラを挿入し、子宮の中を直接観察する方法。(約10分程度)
腹腔鏡検査は、卵管疎通性検査の子宮卵管造影法にて、異常が認められると行われるケースが多くなります。
子宮鏡検査は、経腟超音波検査や、子宮卵管造影法で確認できなかった原因も確認することができます。
| 確認できる原因・病気 | ・子宮内膜症 ・卵管周囲の癒着 ・子宮内膜ポリープ ・子宮粘膜下筋腫 ・子宮体がん ・悪性疾患の有無 など |
| 検査に適した時期 | 検査方法により異なる |
基本検査で確認できなかった原因をより詳しく調べることができますので、医師から勧められた場合は受けることをおすすめします。
8. MRI検査を行う|子宮内膜症がないか調べる
MRI検査は超音波検査などで、子宮内膜症や子宮筋腫、子宮腺筋症などが疑われる場合に追加で受ける検査です。
MRIの装置の中に入り、磁場を用いて体の断面画像を撮影する方法(所要時間約30~40分程度)
です。
| 確認できる原因・病気 | ・子宮内膜症 ・子宮筋腫 ・子宮腺筋症 |
| 検査に適した時期 | いつでも |
MRI検査を行うことで、子宮内膜症などの進行度合いをより正確に知ることができます。
MRI検査は専用の装置が必要なため、検査を受けられない医院もあります。その場合は提携院を紹介してくれますので、紹介状を持って指定医院へ検査へ向かいましょう。
また、各検査を行った後の不妊治療方法に関しては、別記事にて解説しています。不妊治療法まで詳しく知りたい方は、今回の記事と併せて目を通してみてください。
【男性】病気の可能性もある子供ができない原因3つ
記事の冒頭でもお伝えした通り、子供ができない原因は女性だけでなく、男性側にもありえます。
ここからは不妊の原因が男性側にある場合に、どんな病気の可能性があるのかをお伝えしていきます。
病気の原因や治療法についても詳しく解説していきますので、それぞれ確認していきましょう。
1. 造精機能障害が原因|精子を作る過程で精子が減少する
男性不妊の約80~90%の原因は、造精機能障害と言われています。造精機能障害は精子をつくる機能に問題があることで、射精した精子の数や運動量が低下し受精が難しくなります。
| 造精機能障害になる原因 | ・原因不明…約半数 ・精索静脈瘤…約40% ・ホルモン低下…約1% |
| 造精機能障害の種類 | ・無精子症…精子が見つからない状態 ・乏精子症…精子の数が少ない状態 ・精子無力症…精子の運動率が悪い状態 |
| 治療法 | ・原因不明…生活習慣の改善や抗酸化剤のサプリメント、漢方による治療 ・精索静脈瘤が原因…精索静脈を結さつ(縛って結ぶ方法)や切断する手術 ・ホルモン低下が原因…ホルモン注射による治療 |
| 検査方法 | ・精液検査 ・ホルモン採血 ・尿検査 |
また、ホルモン低下が原因の場合は、下垂体性性腺機能低下症(性ホルモンの分泌低下)、精巣形成不全症候群(精巣機能の悪化)といった病気の可能性もあります。
2. 性機能障害が原因|勃起や射精がうまくいかない
男性不妊の原因には、勃起や射精に支障をきたす性機能障害があります。性機能障害があると満足した性行為が行えず不妊となってしまいます。
| 性機能障害になる原因 | ・身体的要因 ・心理的要因 |
| 造精機能障害の種類 | ・勃起障害(ED)…勃起を維持できない状態 ・射精障害…射精がうまくできない状態 ・性欲障害…性欲が低下している状態 |
| 治療法 | ・勃起障害…バイアグラなど薬剤の服用 ・射精障害…リハビリンやカウンセリング、薬剤の服用 ・性欲障害…カウンセリング、ホルモンの補充療法 |
| 検査方法 | ・ホルモン採血 ・内科検査 |
性機能障害は子供ができないことが精神的なストレスとなり、問題を悪化させてしまうこともあります。
また、性機能障害は加齢や生活習慣病との関連も疑われますので、内科検査を含め総合的な検査を受けるのがおすすめです。
3. 精路通過障害が原因|精液の通り道が閉鎖され精子が出てこられない
精路通過障害は、精子の通り道が詰まってしまい塞がっている状態です。精子が外に出られない状態のために不妊となります。
前立腺液や精嚢液(精液の90%以上を占める液体)の射精は行えるため、自覚症状がありません。原因は先天性のものと後天性のものがあります。
| 精路通過障害になる原因 | ・先天性精管欠損症…生まれつき精管が形成されていない状態 ・尿道炎…病原菌が尿道の粘膜に感染し炎症を起こした状態 ・射精管閉塞症…病原菌が尿道の粘膜に感染し射精管を塞いだ状態 |
| 治療法 | ・詰まったり欠損したりした部分の再建手術 ・体外受精 |
| 検査方法 | ・超音波検査 |
ただし、中には原因不明のものもあり、自覚症状がないため発見が遅れてしまう可能性が高くなっています。
男性不妊についてもまずは早期発見・早期治療が大切です。女性だけでなく男性も一緒に不妊検査へ行くようにしましょう。
また、男性不妊についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事もチェックしてみてください。
【男性】子供ができない原因や病気がわかる検査方法4選
男性側の不妊に関わる病気についてわかったところで、それぞれの病気を見つける検査方法をお伝えしていきます。
男性も女性同様「どんな検査をされるんだろう?」「検査で何がわかるの?」と不妊検査への不安や疑問は少なくありません。
男性の不妊検査の方法
・精液検査
・ホルモン採血
・超音波検査
・尿検査
男性不妊の検査は採血や超音波、尿検査など、病院での診察や健康診断でも経験のあるような検査方法です。
それぞれの検査方法について詳しくは、続いて解説していきますので検査内容を詳しく見ていきましょう。
1. 精液検査をする|造精機能障害であるか調べる
精液検査は造成機能障害の有無を調べる検査です。
検査の流れ
1.問診
2.2日~約1週間の禁欲(射精しない期間)
3.自宅又は病院の採精室で採精容器に精液を採取
※自宅で採取した場合は1時間以内には病院へ持参するようにしましょう!
4.顕微鏡にて精液の確認と説明
5.濃度などの検査結果は約1週間後に通知
| 検査する項目 | ・精液の量や濃度 ・精子の運動率 ・精子の形態 |
| 精液検査でわかる原因・病気 | ・無精子症 ・乏精子症 ・精子無力症 ・奇形精子症 |
精液は、採取日の体調やストレス度合いによっても数値が変化します。1度悪い結果が出たからといって病気であるとは限りません。
別の日に再検査を受けることで問題がないケースもあります。さらに精液の性状(性質や状態)には生活習慣も大きく関わっています。
喫煙や過度の飲酒、過度の肥満は精液に悪影響を与えることも。規則正しい健康的な生活も心がけていきましょう。
2. ホルモン採血を行う|造精機能障害・性機能障害か調べる
ホルモン採血とは、造精機能障害に加え、性機能障害について調べる検査です。血液検査により、男性不妊に関係するホルモン数値を確認します。
| 検査する項目 | ・黄体形成ホルモン…男性ホルモンの分泌に関わるホルモン ・卵胞刺激ホルモン…精子をつくり出す機能に関わるホルモン ・テストステロン…精子をつくるのに必要なホルモン ・プロラクチン…EDや不妊症の原因となるホルモン |
| 精液検査でわかる原因・病気 | ・勃起障害 ・射精障害 ・下垂体性性腺機能低下症 ・無精子症 ・乏精子症 |
採血結果は後日に通知されることがほとんどです。無精子症の場合には、ホルモン検査の他に染色体や遺伝子検査も追加で行うケースもあります。
3. 超音波検査をする|精路通過障害が原因か調査する
超音波検査では造精機能障害の原因や精路通過障害の有無を検査できます。
検査の流れ
1.問診
2.超音波を発する器具(プローブ)を対象部位に当てる
3.モニターで画像を確認
4.結果はその場で通知
| 検査する項目 | ・精巣の大きさ ・精巣の結石やかたまり ・精管 ・前立腺 ・尿道 など |
| 精液検査でわかる原因・病気 | ・精索静脈瘤 ・精巣がん ・精子の通り |
精索静脈瘤や精巣がんは、超音波を発する器具(プローブ)を陰嚢(睾丸)に当て確認していきます。
精液検査で無精子症と診断された場合には、経直腸的超音波検査を行います。経直腸的超音波検査は肛門から器具(プローブ)を挿入し、精子の通り道に問題がないかを確認します。
器具(プローブ)といっても人差し指ほどの太さのものです。肛門への挿入は不快感を感じる方も多いですが、痛みに配慮されていますので安心して検査を受けてみてください。
4. 尿検査をする|造精機能障害であるか調べる
尿検査では、造精機能障害や精路通過障害について調べます。
| 検査する項目 | ・尿糖 ・尿蛋白 ・潜血 ・赤血球 ・白血球 など |
| 精液検査でわかる原因・病気 | ・炎症細胞 ・腎臓や膀胱の異常 ・前立腺炎 ・精巣上体炎 |
精子の通り道と尿の通り道は、尿道で重複しています。精子の通り道に炎症があると、精子の活動量が弱まり不妊になることも。
また、精巣上体炎が悪化していくと、精子の通り道が塞がり精路通過障害となってしまいます。
さらに炎症が起こっている原因が、クラミジアや淋菌といった性感染症の場合、女性側へ感染させてしまう危険性も!
不妊の原因には、男女ともに感染してしまう病気が隠されているケースがあります。夫婦揃って検査を受けることで、不妊の原因を詳しく突き止めることが可能です。
記事の前半でもお伝えした通り、年齢を重ねるほど子供ができない確率も高くなります。不妊検査をスムーズに進め、早めに不妊治療を開始していきましょう。
子供ができない場合に試したい!子供ができやすい体を作る方法5選
子供ができない原因が病気にある場合は、病気に合った治療が必要となります。
しかし、病気がない場合や、妊活に取り組み始めたばかりの方は、こちらでご紹介する子供ができやすい体づくりを参考にしてみてください。
子供ができやすい体づくりのポイント
・ストレスをためない
・適度な運動
・バランスの良い食生活
・体重管理
・喫煙や飲酒を控える
ここからは、それぞれ不妊対策におすすめできる理由と詳しい方法をお伝えしていきます。
1. ストレスをためないようにする
仕事や日々の疲れでストレスを感じていませんか?また、「子供ができない…」という焦りや不安がストレスとなっていることもあります。
ストレスはホルモンを作る正常な機能を乱し、その機能を低下させてしまうことで排卵に影響を与える可能性があります。
ストレスを解消していくためには、心身共にリラックスできる環境を整えることが大切です。
おすすめのストレス解消方法
・誰かに悩みを聞いてもらう
・睡眠をしっかり取る
・趣味(好きなこと)に没頭する
・美味しいものを食べる
・深呼吸をする
・体を動かす
他にも、仕事でストレスを抱えている場合には、一旦仕事をセーブして思い切った休養を取ってみるのがおすすめです。
ストレスにより正常な機能に影響を及ぼさないよう、上手にストレスの発散を行っていきましょう。
2. 適度な運動を習慣にする
「座って過ごすことが多い…」「移動は車や電車が多い…」など運動不足になっていませんか?
運動不足になると、基礎代謝が下がり血流も悪くなります。血液は酸素や栄養素を運んでいるので、血流が悪くなると生殖器官の働きが低下してしまう可能性も!
運動不足を解消するためには、適度な運動を取り入れるのがおすすめです。過度な運動をする必要はありませんので、おすすめの方法をチェックしていきましょう。
適度な運動におすすめの方法
・ウォーキング(散歩)
・ジョギング
・ストレッチ
・ヨガ
無理をする必要はないので、自分ができる範囲で簡単な運動から生活の中に取り入れていきましょう。
運動は夫婦揃って行うのもおすすめ!夕食の後夫婦で散歩に出かけたり、ヨガのペアレッスンへ行ったりと継続できる方法を探してみてください。
3. バランスの良い食事を心がける
「朝食は抜いている…」「昼はコンビニ弁当!」など食生活が乱れていることはありませんか?
人の体は食べ物でつくられていると言われています。体の中の栄養やホルモンバランスを整えることで、卵子と精子が元気に育つ効果が期待できます!
おすすめの食事方法
・1日3食が基本
・朝昼夕と決まった時間に食べる
・栄養素をバランスよく摂る
・食事を抜くダイエットはしない
特にたんぱく質・糖質(炭水化物)・脂質・ビタミン・ミネラルは、5大栄養素となっています。1日の目安摂取量を守り、バランスよく各栄養素を取り入れるようにしていきましょう。
温かい料理で血流を良くすることも大切。冷たい飲み物や食事は控え、体の中から妊娠しやすい体づくりを始めてみてください。
4. 体重を適正にする
「健康診断で肥満と言われた…」「過度なダイエットで痩せすぎた…」ということはありませんか?
女性であれば骨盤内の血流の滞りで、生殖器官の働きが低下。肥満は月経不順・排卵障害の原因に、低体重は無月経・無排卵の原因となります。また、男性の肥満は、体の機能が低下し勃起力や射精能力が下がる原因にも。
BMI値の確認方法
BMI=体重(kg)÷身長(m)×身長(m)
BMIとは身長からみた体重の割合を示す体格指数です。BMI22が理想と言われており、BMI20~24であれば問題ありません。
しかし、BMIが25以上の場合は肥満、BMI18.5以下の場合は低体重となりますので、体重の適正化を目指すのがおすすめ!
無理なダイエットや過剰な食事をする必要はありませんが、BMIの数値を意識した生活習慣を身につけていきましょう。
5. 喫煙や飲酒を控える
「旦那が煙草を吸っている…」「毎晩の晩酌が欠かせない!」など、煙草やお酒などの嗜好品を過度に摂取していませんか?
男性の喫煙はさまざまな研究データから、煙草を吸わない人よりも精子の数の減少や勃起不全のリスクが高まるとも言われています。また、女性も喫煙による血流悪化や体の酸化が原因で、排卵障害や卵子の老化が起こる可能性も!
子供ができないと悩んでいるなら、煙草は禁煙に踏み切るのがおすすめ!そして飲酒は適量を守るようにしましょう。
適度な飲酒の目安は厚生労働省により定められているので、参考にしてみてください。
引用:厚生労働省「アルコール」
アルコールで約20gの目安
・ビールで中ビン1本程度(500ml)
・缶チューハイ1缶程度
・ワイングラス1杯
・日本酒1合程度
規則正しく健康的な生活習慣が、子供ができやすい体づくりへと繋がります。夫婦で協力し合いながら、改善に取り組んでいきましょう!
子供ができない原因を検査し、今すぐ買えるピルで不妊予防をスタートしよう!
不妊は治療が必要な場合、なるべく早く治療に取り組むことが大切です。治療が必要かどうかは、こちらの記事でご紹介した不妊検査で確かめられます。
子供ができない原因がわからずに月日が流れてしまうと、出産の適齢期を過ぎ妊娠しにくい年齢になってしまうことも…。
まずは夫婦で話し合う機会を持ち、各検査方法などを確認した上で、病院へ足を運んでみてください。
また、子供ができない原因となる子宮内膜症や、月経不順は低用量ピルで予防可能です。
低用量ピルは病院まで診察を受けに行かなくても、オンライン診療で処方してもらうこともできます。不妊予防も行いながら、妊活に取り組んでいきましょう!