「最近生理が長いのが気になるけれど、もしかして病気なの?」とお悩みではありませんか?
生理が長い原因は、婦人科系の病気やホルモンバランスの乱れが原因の可能性があります!
そのため、症状から原因を突き止め、治療やセルフケアを行うことで長い生理を改善する効果が期待できます。
そこで今回は、生理が長い原因や長い生理を改善する対策法について詳しく説明します。
原因となる病気やホルモンバランスの乱れによる症状についても紹介するので、セルフチェックも可能です。
この記事を読み終えていただければ、長い生理への不安や生理が長いことによるイライラなどの不調が解消されます。
長い生理への不安を解消して正常な状態に戻したい方は、ぜひ参考にしてみてください!
記事まとめ
・正常な月経の長さや周期・・・25~38日の間に、3~7日ほど月経が継続
・月経が長い原因・・・子宮内膜症や子宮筋腫などの病気や、ストレスなどで起こるホルモンバランスの乱れなど
・月経で起こりやすいトラブルと対策・・・病気の場合は産婦人科で治療が最善!病気以外の原因はセルフケアや低用量ピルで改善可能!
正常な月経とは?
月経周期とは、月経の開始日から次の月経の前日までの日数を指します。
正常な月経周期とされる25~38日の間、次の4つの周期によって成り立ちます。
正常な月経周期
1.月経期:月経が継続している期間
2.卵胞期:月経が終了して、卵胞ホルモン(エストロゲン)の分泌が増える時期
3.排卵期:排卵日付近
4.黄体期:排卵後から次の月経まで黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌が増える時期
正常な月経期間は3~7日、平均すると5日程度とされています。
月経が長引いている場合、特に気を付けたいのは、生理が長引く「過長月経」と経血量が増える「過多月経」です。
「過長月経」や「過多月経」が引き起こされる原因には、子宮や卵巣の病気が隠れている場合も。
生理が8日以上続く場合は以下を参考に当てはまるかどうかセルフチェックしてみてください。
| 種類 | 特徴 | 原因となる病気 |
| 過長月経 | 8日以上と長い | 子宮筋腫や子宮腺筋症、無排卵周期症 |
| 過多月経 | 総出血量が140ミリリットル以上 ナプキンを1時間ごとなど頻回に交換。昼でも夜用のナプキンを使用。レバー上の凝血塊が混ざっている |
子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜症、子宮内膜ポリープ、子宮内膜増殖症 |
ただし、必ずしも病気が原因ではなく、ストレスなどによるホルモンバランスの乱れが原因の可能性もあります。
月経期間が長かったり、明らかに経血量が多かったりする場合、貧血症状を起こす可能性もあるので早めの対処が大切!
病気の場合は産婦人科で治療、病気以外の場合はセルフケアやピルを服用するなど、原因に合わせた対処法で長引く生理を改善しましょう!
生理が長いのはなぜ?原因となる病気8選
月経が長いくと、身体の不調が続き、精神的にも辛い時期が長いことになります。
自分の症状に当てはまる病気や原因となる習慣が見つかれば、長い生理を正常に戻す方法がわかります。
そこで、生理が長い原因となる病気や検査方法、症状について解説します。セルフチェックの参考にしてみてください。
1. 「子宮筋腫」が原因|子宮の筋腫にできる良性の腫瘍
子宮筋腫とは子宮の筋肉に硬い線維性のこぶができる病気。
原因は不明とされています。
筋腫ができることで、子宮の表面積が大きくなります。月経時に剥がれ落ちる子宮内膜の量が増え、生理が長くなる過多月経の原因となります。
月経が長い以外に、子宮筋腫で起こる主な症状は次の通りです。
| 主な症状 | 経血量の増加、月経の延長、月経痛、不正出血、貧血症状、膀胱の圧迫症状、腹部を触ると腫瘍に触れる |
| 痛みの程度・出血量 | 月経時の腹痛や腰痛。月経時以外に生じることもある。以前に比べ出血量が多くなってきた自覚。血の塊が混ざる |
子宮筋腫の有無や状態を調べるためには、産婦人科を受診して検査を行う必要があります。
| 検査名 | 検査の内容 |
| 内診 | 子宮筋腫の大きさや位置を確認 |
| 超音波検査 | 子宮筋腫の大きさや位置を確認 |
検査結果から子宮筋腫であると診断されても、筋腫がまだ小さい・数が少ない段階ではすぐに治療を受けなくて良い場合も。
痛みや貧血といった症状を取り除きながら、定期的に検診を受けるだけでも良いという方も多いです。
筋腫が大きくなったり、不妊の原因となりうると判断した場合に、以下の薬物療法や手術療法に踏み切ります。
| 治療名 | 治療方法 |
| ホルモン薬の内服* | Gn-RHアナログ、男性ホルモン様作用のある薬剤(ダナゾールなど)を使用 |
| 筋腫核出術 | 病巣のみを摘出する方法。妊娠を希望する場合に適応 |
| 子宮全摘術 | 子宮全体を摘出する方法。妊娠を希望しない場合適応 |
| カテーテルによる子宮動脈塞栓術(UAE)** | 子宮の栄養血管を止めることで、こぶを小さくする |
| マイクロ波子宮内膜焼灼術(MEA)*** | マイクロ波で子宮内膜を焼灼し、こぶを凝固させる |
| 自覚症状だけ取り除く | 鉄剤投与による貧血治療 |
症状が当てはまるという方は、お早めに産婦人科を受診しましょう。
2. 「子宮腺筋症」が原因|子宮内膜が変形・拡張
子宮線維症とは、何らかの原因で子宮内膜が子宮の奥(筋層部)まで入り込み、子宮内膜の細胞が増えてしまう病気。
もぐりこんだ子宮内膜の細胞が増えることで、子宮内膜が厚くなってしまい、月経時の出血量が増えます。
出血量の増加と不正出血も見られるので、生理が長い原因となる場合も。
子宮線維症の主な症状は次の通りです。
| 主な症状 | 経血にレバーのような血の塊が混ざる、貧血、下腹部痛、不正出血、排便痛 |
| 痛みの程度・出血量 | 強い月経痛や下腹部痛、腰痛を引き起こすが、無症状で検査で発見されるケースもある。出血量が多く、月経が長引く |
子宮線維症の診断や他の疾患との識別のためには、次のような検査が行われます。
| 検査名 | 検査の内容 |
| 問診 | 自覚症状の有無や程度を確認 |
| 内診 | 子宮、卵巣の可動性や痛みの有無を確認 |
| 超音波検査 | 子宮や卵巣の腫大の有無を確認 |
| MRI検査 | 約50%が子宮筋腫を合併しており、状態の診断にはMRIが最も有用 |
| 腫瘍マーカー(CA125) | 一般に卵巣がんの識別に使われるが、婦人科疾患でも高値を示す |
検査結果で子宮線維症と診断された場合、薬物療法と手術療法が用いられます。
根治(根本的に治る)のは子宮全摘出となり、他の選択肢は症状を和らげる対症療法となります。
| 治療名 | 治療の内容 |
| 低用量ピルの内服 | 症状の進行を抑えられる。副作用が少なく、安価で長期間使用可能 |
| プロゲスチン経口剤の内服 | 症状の進行を抑え、症状を改善させる。不正出血などの副作用を伴うが、疼痛改善率が高い。高血圧症や喫煙習慣のある女性でも適応可能 |
| GnRHa療法の内服 | エストロゲンを低下させることで病変を縮小させる。閉経が近い女性が手術を回避する「逃げ込み療法」。手術前の補助療法 |
| 子宮腺筋症核出術 | 病巣が限局している場合や長期の不妊の原因となっている場合。根治には至らない |
| 子宮全摘術 | 薬物療法で症状の改善を認めず、閉経までの期間が長い場合。唯一の根治術 |
| 自覚症状だけ取り除く | 鉄剤投与による貧血治療や鎮痛薬の内服 |
気になる症状がある場合は放置せず、お早めに産婦人科を受診してください。
3. 「子宮内膜増殖症・子宮体がん」が原因|子宮内膜が以上に分厚く増殖
子宮内膜異型増殖症とは、エストロゲンの過剰分泌により、子宮内膜という組織が異常に分厚く増えてしまいます。
その結果、子宮内膜の細胞が正常な細胞と形が異なってしまう病気です。
また、子宮体がんは子宮体部(子宮の上部2/3)に発生するがん。
子宮内膜増殖症は子宮体がんを発症する前段階とされており、発がん率は3割程度とされています。
子宮内膜が異常に厚く増えてしまうと、月経時に剥がれ落ちる子宮内膜の量が多いため、出血量が増え、生理が長い原因となります。
参照元:Felicia Trial
子宮内膜増殖症および子宮体がんで起こる主な症状は、次の通りです。
| 主な症状 | 月経痛,慢性下腹部痛,性交痛,排便痛、貧血 |
| 痛みの程度・出血量 | 経血量が多い、月経期間が長い、月経時以外の不正出血 |
子宮内膜増殖症および子宮体がんが疑われる場合、細胞異型の状態(前がん状態か、あるいはがんの進行度合いや転移の有無)の確認や、他の疾患との識別のために次のような検査を行います。
| 検査名 | 検査の内容 |
| 経腟超音波検査 | 子宮内膜の厚さを確認 |
| 子宮鏡検査 | 内視鏡を用い、病変の位置や形状を確認 |
| CTおよびMRI検査などの画像診断 | がんの場合、転移や、筋層まで浸潤の有無など病変の広がりを確認 |
| 細胞診・組織診 | 細胞や組織異常を確認 |
| 血液凝固・肝機能検査 | 子宮温存療法の適応となるかを確認 |
子宮内膜増殖症や子宮体がんと診断された場合、以下の薬物療法や手術療法などの治療を開始します。
| 治療名 | 治療の内容 |
| メドロキシプロゲステロン(MPA)の内服 | 乳がんと子宮体がんに適応のある薬剤。妊娠を希望する場合の妊孕性温存療法。 |
| 手術による摘出 | がん化の頻度が高さや、4割ほどがんが併存しているため、子宮体がんに準じた治療を行う |
| 化学療法・放射線治療 | がんの進行具合や年齢、妊娠・出産の希望などを考慮して行うことがある。 |
がんは早期発見・早期治療することが大切です。お早めに産婦人科を受診しましょう。
4.「 子宮内膜ポリープ」が原因|子宮内膜の細胞が以上に増殖
子宮内膜ポリープとは、子宮内膜の細胞が過剰に増殖し、子宮内腔に2~4cm大の腫瘍(ポリープ)ができる病気。
子宮内膜ポリープの大きさや位置によっては、卵管で受精した受精卵が子宮内にもどってきてしまい、着床できず、不妊の原因となります。
大半が良性ですが、ごくまれに悪性のものもあります。
子宮内膜ポリープはエストロゲンによって過剰に子宮内膜が増殖することが原因とされています。
ポリープにより子宮内の表面積が大きくなるため、月経時に出血が止まりにくくなって月経が長引いたり、出血量が多くなります。
子宮内膜ポリープは無症状な場合が多いですが、自覚症状として次のような症状が現れることがあります。
| 主な症状 | 月経期間が長い、月経以外の出血、下腹部痛、貧血、閉経後の性器出血、不妊 |
| 痛みの程度・出血量 | 経血量が多い、月経期間が長い、月経時以外の不正出血 |
自覚症状が出づらいため、たまたま婦人科を受診して超音波などの検査を受けて、診断されたという人も少なくありません。
他の疾患との識別や診断の確定のために、子宮細胞診や病理組織検査などで詳しく検査することもあります。
| 検査名 | 検査の内容 |
| 経腟超音波検査・MRI | 子宮内腔の状態を観察 |
| 子宮鏡検査 | 膣から子宮の中に細いスコープを入れ、子宮内腔のポリープの個数や位置、大きさ、ポリープ表面の性状を確認 |
| 子宮内膜細胞診・病理組織検査 | 子宮内腔表面の細胞を内診台で採取して、顕微鏡で確認。悪性か判断 |
全ての子宮内膜ポリープに治療が必要な訳ではなく、良性で無症状だと経過観察とする場合もあります。
| 治療名 | 治療の内容 |
| 内膜掻爬術 | 子宮内膜を掻爬して、ポリープを摘出 |
| 子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 膣から子宮の中にスコープをいれ、ポリープを切除する手術。ポリープの個数や位置、大きさによっては、外来手術(日帰り)が可能 |
子宮内膜ポリープを治療する場合、薬剤では効果が得られにくいため、切除する方法が完治を目指せるとされており、上記のような方法が用いられます。
5. 「子宮頸がん」が原因|性交渉時の感染によるもの
子宮頸がんとは、子宮頸部(子宮の下部1/3)や子宮頸管の上皮から発生したがん。
性交によるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因とされています。
子宮頸がんが原因で出血がダラダラと長期間続くのは、月経自体は終了しても、癌部分からの出血が起きている状態です。
初期の子宮頸がんでは自覚症状がありませんが、進行してくると次のような症状が現れるようになります。
| 主な症状 | 不正出血、性交後の出血、茶褐色や黒褐色のおりものの増加、経血量が多い、月経期間が長引く、下腹部や腰の痛み |
| 痛みの程度・出血量 | 経血量が多い、月経期間が長い、月経時以外の不正出血 |
子宮頸がんが疑われる場合、がんの進行度合いや転移の有無の確認、他の疾患との識別のために次のような検査を行います。
| 検査名 | 検査の内容 |
| 細胞診 | 子宮頸部(外子宮口の付近)を綿棒、ブラシ、ヘラのような器具でこすって細胞を採取する検査 |
| 内診 | 子宮や卵巣の状態を、膣から指を入れて調べる |
| 組織診 | 細胞診で異常があった場合、がんが疑われる部分から組織を切り取り、診断を行う |
| 超音波検査 | 超音波検査の器具を膣に入れて子宮頸がんの性状をみたり、腫瘍と周囲の臓器との位置関係などを調べる |
| CT検査・MRI検査 | がんの転移の有無、周囲臓器への広がりを診断 |
子宮頸がんと診断された場合、がんの進行の度合い、腫瘍の大きさ、妊娠の希望の有無、年齢などによって治療を選択します。
初期の子宮頸がんでは、手術による切除が第一選択となります。
準広汎子宮全摘術子宮と膣の一部、基靭帯の一部を切除する
| 治療名 | 治療の内容 |
| 円錐切除術 | がんが早期の場合、子宮口の入口を一部切り取る |
| 単純子宮全摘術 | 子宮全体を切除する方法 |
| 広汎子宮全摘術 | 子宮と膣の一部、基靭帯、リンパ節を切除する |
| 化学療法・放射線療法 | がんの進行具合や年齢、妊娠・出産の予定などを考慮して行うことがある |
産婦人科に抵抗がある方も多いですが、女性医師が診てくれるクリニックも多いです。
生理が長引いている場合や気になる症状がある場合は放置せず、お早めに受診しましょう!
6. 「更年期障害」が原因|卵巣の機能が低下
女性は40歳以降になると、卵巣の機能が低下することでエストロゲンの分泌が減少し、ホルモンバランスが乱れます。
一般に閉経は50歳ごろとされており、更年期は閉経前後の5年にあたる45~55歳頃。
更年期ではホルモンバランスの乱れによる月経不順だけでなく、過長月経も引き起こします。
エストロゲン以外にプロゲステロンの分泌も減少するため、子宮内膜が充分に厚くならずにすぐ剥がれて排出されてしまい、ダラダラと月経が長引く原因になります。
更年期の女性は全身症状、精神症状、月経の異常が主な症状としてあらわれます。
| 主な症状 | のぼせ、ほてり、精神不安定、貧血(めまい)、頭痛、息切れ、動悸、顔色が悪い、頻発月経、稀発月経、過長月経 |
| 痛みの程度・出血量 | 少ない出血量がダラダラ続く、月経が終わらないまま次の月経が来ることもある |
45歳以降の女性は、月経の異常を更年期によるものと決めつけて自己判断せず、産婦人科の受診を検討してみましょう。
更年期による卵巣機能の低下に伴う月経異常が疑われる場合、他の疾患との識別のために次のような検査を行います。
| 検査名 | 検査の内容 |
| 問診 | 月経の状態や自覚症状の内容 |
| 内診・超音波検査 | 子宮や卵巣の形態に異常がないか調べる |
| 血液検査 | 女性ホルモンの値(エストロゲン・プロゲステロン)を調べる |
参照元:Doctors me
更年期の症状を和らげるためには、不足しているホルモンの補充や、自覚症状に応じた対症療法が必要になります。
| 治療名 | 治療の内容 |
| ホルモン補充療法(HRT) | エストロゲン・プロゲステロン併用療法が一般的。子宮摘出を受けた女性はエストロゲン単独療法を行う |
| 漢方薬 | 当帰芍薬散:比較的体力が低下、冷え症、貧血傾向。加味逍遥散:疲労しやすい、不安・不眠などの精神症状。桂枝茯苓丸:のぼせ傾向、下腹部に抵抗・圧痛 |
| 向精神薬 | 精神症状の治療に抗不安薬や抗うつ薬、催眠鎮静薬 |
更年期の症状が軽い場合はセルフケアも有効ですので、試してみてください。
おすすめのセルフケア方法
・規則正しい生活を送る
・三食バランスの良い食事を摂る
・軽い運動をする
・リラックスタイムを設ける
7. 「無排卵月経」が原因|女性ホルモンの分泌異常で起こる
無排卵月経とは、排卵せずに月経のような出血が起きる状態。
排卵に必要なエストロゲンの分泌が少ないので、プロラクチンも充分に分泌されません。
エストロゲンとプロラクチンの不足で子宮内膜は充分な厚さを保てず、すぐに剥がれ落ちてしまい、ダラダラとした出血が続きます。
無排卵月経では、月経期間の延長や不規則な月経周期以外に、基礎体温の異常が症状として現れます。
| 主な症状 | 1年以上妊娠しない、基礎体温に低温期・高温期の変化がない、月経周期が不安定、月経期間が長引く |
| 痛みの程度・出血量 | 経血量が少ない、月経期間が長い |
無排卵月経では基礎体温の体温相の変化に特徴がみられるため、継続的な基礎体温の計測が必要となります。
また、他の疾患との識別のために、婦人科を受診して内診や超音波検査などの検査を行います。
| 検査名 | 検査の内容 |
| 基礎体温を計測 | 3カ月、毎朝起床時の基礎体温を計測し、低温期や高温期の有無や温度差を調べる |
| 内診 | 子宮や卵巣の状態を、膣から指を入れて調べる |
| 血液検査 | ホルモン濃度を調べ、黄体機能やプロラクチンなどのホルモン数値を確認する |
| 超音波検査 | 子宮や卵巣の状態を確認する |
無排卵月経の状態が継続すると、正常に排卵する機能が次第に失われ、不妊の原因となります。
無排卵月経の診断を受けた場合、早期に次のような治療を行う必要があります。
| 治療名 | 治療の内容 |
| 排卵誘発剤 | ホルモン分泌をコントロールし、排卵させる |
| ホルモン剤の服用 | 子宮・卵巣機能を高めて月経周期を整える |
| 原因疾患の治療 | 多嚢胞性卵巣症候群や甲状腺機能の異常など、原因とされる疾患がある場合、それぞれの疾患に応じた治療を行う |
8. 「黄体機能不全」が原因|黄体ホルモンの分泌不足によるもの
黄体とは、排卵後空になった卵胞から作られるもので、プロゲステロンを分泌します。
プロゲステロンは子宮内膜を成熟化させ、月経として体外に排出されるまで支える役割を担います。
黄体機能不全とは、この黄体から充分にプロゲステロンが分泌されない状態。
プロゲステロンが充分に分泌されないので、子宮内膜が充分に厚くなる前に剥がれ落ちてしまい、月経期間が長引いて経血量が多くなります。
高プロラクチン血症、脳の視床下部や下垂体の異常による原因が考えられます。
その他にも年齢的な原因として、卵巣機能が未熟な思春期や、加齢などにより卵巣機能が低下した40歳以降の方に多いとされています。
黄体機能不全は、子宮内膜を支えるプロゲステロンの分泌が不足しているので、排卵後から月経開始までに不正出血や体の不調が起こりやすいという特徴があります。
また、排卵後の高温期の変化など、自覚症状として現れるのは次の通りです。
| 主な症状 | 痛みの程度・出血量 |
| 排卵後の基礎体温が低い、排卵後の高温期が短い、月経周期が短い、排卵後から月経までの期間に不正出血や体の不調(乳房の張りやほてり)、不妊、流産 | 月経が長引く、経血量が多い |
黄体期不全は、卵巣の機能低下以外に、甲状腺機能異常症や高プロラクチン血症といった病気が原因の可能性が考えられます。
そのため、子宮や卵巣の状態を確認したり、婦人科系以外の他の病気と見分けるために次のような検査が行われます。
| 検査名 | 検査の内容 |
| 基礎体温を計測 | 1カ月、毎朝起床時の基礎体温を計測し、低温期や高温期の有無や温度差を調べる |
| 血液検査 | ホルモン濃度を調べ、黄体機能やプロラクチンなどのホルモン数値を確認する |
| 超音波検査 | 子宮や卵巣の状態を確認する |
黄体機能不全では、原因となっている病気や因子(引き起こる元になる要素)への治療を行います。
| 治療名 | 治療の内容 |
| 黄体ホルモンの補充 | 排卵後に黄体ホルモンの補充を行う。妊娠を希望する人に行う |
| 排卵誘発剤 | 黄体機能の改善を図る。妊娠を希望する人に行う |
今後妊娠を希望するかどうかによっても治療方法は異なります。
生理が長い場合は基礎体温を測ることで異常に気がつくこともできるので、習慣として身につけると良いです。
病気ではない場合は低用量ピルがおすすめ!
産婦人科を受診しても、月経が長引く原因が分からないことはあります。
そんなときは、低用量ピルの内服を検討してみましょう!
低用量ピルには、エストロゲンとプロゲステロンという2つのホルモンが配合されています。
女性の身体は月経周期に伴い、ホルモンバランスが大きく変化しますが、このバランスが乱れている状態が「月経不順」というトラブルとしてあらわれます。
月経不順は体の不調だけでなく、精神的な不安やイライラを引き起こし、日常生活や仕事面にも影響します。
ホルモンが含まれている低用量ピルを内服すると、体のホルモンバランスを一定に保つ作用があり、月経に伴うトラブルが起きにくくなるとされています。
低用量ピルは医師の診察が必要なため、産婦人科で処方してもらえます。個人輸入品は危険なので絶対に購入しないようにしましょう。
今すぐ低用量ピルを処方したい方は、オンラインピル処方がおすすめ。
・最短で翌日にはピルが手元に届く
・産婦人科に行く必要がない
・誰にもバレない
当日中でも診察の予約が取りやすく、最短翌日に到着します。他のサービスでもありがちな、煩わしいアプリも不要ですよ。
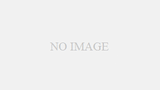
茶色の血や鮮血は大丈夫?気になる生理のギモンQ&A5選
「月経がいつもと違うような…」と気になる症状があっても、中々周りに相談できなくて困ってしまう女性は多いです。
そこで、産婦人科を受診する目安として、よくある月経時のトラブルやお悩みをご紹介します。
1. 茶色の血が出るのは病気?
月経期間ではないのに、濃い茶色のおりものが出たり、おりものに茶色い血液のようなものが混ざっていることがあります。
月経以外の出血は、「不正出血」と呼ばれます。
茶色の血がでる原因として考えられるもの
・茶色い出血は、出血から時間が経って酸化したため、茶色っぽく変化したもの
・月経前後の茶色い出血やおりものは、月経前の微量な出血や月経後の子宮内に残った血液の排出などが主な原因
ただし、茶色の出血が長期間続く場合は、癌やポリープなど、思わぬ病気が潜んでいる可能性があります。
不正出血を引き起こす病気は次の通りです。
| 器質性出血 | 子宮や卵巣、膣に何らかの異常・疾患があって起こる出血。宮頚がん、子宮体がん、子宮筋腫、子宮内膜症、膣炎、子宮膣部びらん、子宮頚管ポリープなど |
| 機能性出血 | 病気や妊娠と関係なく、女性ホルモンのバランスの乱れで起こる出血。思春期や更年期など。< |
| 中間期出血 | 月経の排卵期に起きる少量の出血。異常はないとされる。 |
| その他の出血 | 妊娠初期に起こる着床出血や、性行為で膣が傷ついたときの外傷など。 |
茶色い出血が続く場合は産婦人科の受診を検討してみましょう。
2. 鮮血が出るのは危険?
月経期間以外での鮮血の不正出血は、出血量が多いか、子宮や膣の入口付近で出血している可能性があります。
「月経不順かもしれない」「少量の出血だから大丈夫だろう」と自己判断で放置していると、不妊の原因になったり、病気の発見の遅れにつながります。
病院受診の目安は次の通りです。
病院受診の目安
・出血量が多い
・強い痛みを伴う
・不正出血を繰り返している
・閉経後の出血
・2週間持続する出血
出血部位や原因を特定するために、「生理が長い日が続いている」という場合は産婦人科の受診を検討しましょう。
3. レバー状の血が出る場合は?
経血は子宮の内膜が剥がれ落ちる際に出血が起こり、一度固まった血液が酵素の働きで再び溶かされて体外に排出されます。
しかし、子宮内膜が厚くて出血量が多い場合、酵素の量が足りずに溶かしきれず、レバーのような塊として排出されることがあります。
20代後半や30代の若い女性は子宮内膜を成長させるエストロゲンの分泌が多いため、レバーのような塊が混ざっていても、珍しいことではありません。
ただし、レバー状の塊の量は出血量にも直結するので、貧血症状が出現することもあります。
貧血の症状
・身体がだるく疲れやすい
・耳鳴り、動悸(どうき)、息切れ、めまいなど
・毎月少しずつ貧血が進行した場合には自覚症状が乏しい
また、頻繁にレバー状の塊が出る場合は、子宮筋腫や子宮腺筋症などの病気のサインの可能性が考えられます。
月経時に排出される塊の量や頻度を注意深く観察しましょう。
4. 妊娠の可能性はある?
妊娠初期の4週頃、着床出血で3日ほど出血することがあります。
着床出血とは、受精卵が子宮内膜に着床する際、子宮内膜を傷付けることで起こる出血です。
着床出血の特徴
・通常の月経と比べて出血量が少ない
・出血期間は1~2日程度、長くて3~4日程度
・出血の色はおりものに血液が混ざったピンク色や赤色、鮮血色
・月経痛に比べて軽い着床痛が生じることがある
妊娠による着床出血の可能性がある場合、安易に自己判断せず、妊娠検査薬の使用や産婦人科受診で妊娠の有無を確認しましょう。
参照元:ミネルバクリニック
5. 生理が長い原因はピルの服用?
低用量ピルは子宮内膜が剥がれ落ちないように作用します。
月経初日から低用量ピルの内服を開始すると、低用量ピルの働きによって経血の排出が抑制されるので、少量の出血が1~3週間続きます。
ただし、出血量が多い場合や2週間以上月経が続く場合、低用量ピル以外の出血である可能性が考えられますので、産婦人科を受診しましょう。
生理が長いときは産婦人科で相談してみよう!
月経が長引いている原因や疾患を特定するためには、産婦人科を受診し、医師による検査を受けることが望ましいです。
「単なる生理不順だから大丈夫」と安易に考えるべきではありません。
婦人科疾患は不妊の原因になったり、がん化する疾患もあるので、できるだけ早く治療を開始し、状態の改善を目指しましょう。
また、不規則な生活やストレスなどが原因の月経不順には、ホルモンバランスを整えてくれる低用量ピルの内服も有効な手段の一つ。
忙しい方や、お近くに産婦人科がない方であれば、オンライン診療の利用がお手軽でおすすめです!

