生理周期を把握するのは、避妊したい場合、妊娠したい場合、どちらにおいても大事なことです。また生理周期を知ることで、体の不調を知るきっかけになることもあります。
この記事では、女性として知っておきたい生理周期の計算方法、正常値などについてお伝えします。生理は女性にとって、切っても切れない身近なもの。ぜひ生理周期について知って、毎日の生活に役立ててください。
生理周期の計算方法
生理周期を把握するにあたって、「生理周期ってどこから数えるの?」と気になりますよね。生理の初日を1日目として数え、次回の生理が始まる前日までが、1回の生理周期とカウントされます。
個人差はありますが、正常な生理周期は25日~38日程度、生理の期間は3~7日間と言われています。自分の生理周期を知るために、生理の初日と終了日を半年程度控えて、平均値を計算してみましょう。
生理周期が比較的安定している人でも、1~2日程度のズレはよくあるもので、毎回きっちり同じ日数で生理周期が繰り返されている人は稀です。生理周期が安定している人も、一度生理周期の平均値を計算してみることをおすすめします。計算が面倒な場合は、生理に関するスマホアプリを活用しましょう。生理日を毎回登録しておくと、自動で計算されます。
例外として、生理が始まったばかりの10代、更年期を迎える時期は、生理周期が乱れやすくなります。また閉経が近づいてくると、生理周期が2ヶ月、3ヶ月と少しずつ伸びていきます。1年間生理がこなければ、閉経と診断されます。
生理周期とは
生理周期は、「卵胞期」「排卵期」「黄体期」の3つの時期に分けられます。それぞれの時期ごとに、ホルモンの量、子宮内膜の状態、体温などが変わっていますので、時期の特徴と合わせてご紹介します。
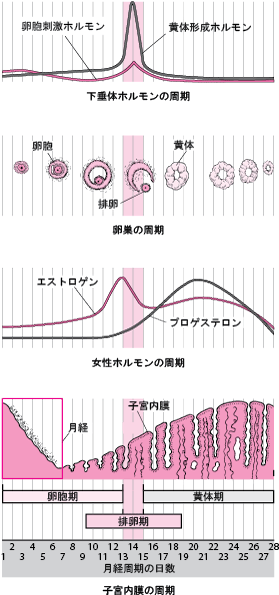
引用:月経周期 ? 22. 女性の健康上の問題 ? MSDマニュアル家庭版
卵胞期
卵胞期は、生理の1日目から始まり、平均して14日程度続きます。「低温期」とよばれる、基礎体温が低めの期間が続きます。肌の調子が良かったり、ダイエットが成功しやすかったりする「キラキラ期」と呼ばれる時期も、この中に含まれています。
卵巣にある卵胞が発達するのが、主な特徴です。月経が起こる頃に、「卵胞刺激ホルモン」の分泌量が少し増加し、このホルモンにより卵胞が成長し始めます。
女性ホルモンの「エストロゲン」「プロゲステロン」がほぼ一定に保たれているので、ホルモン量の変動によるメンタルへの影響も出にくいです。エストロゲンの量が急上昇すると、次の排卵期に入ります。
排卵期
排卵期は、16~32時間程度続いて、排卵が終わると黄体期に入ります。排卵期には基礎体温の変化があり、「低温期」から「高温期」に移り変わります。
排卵期には、「黄体形成ホルモン」が多量に分泌されます。黄体形成ホルモンの刺激により、卵胞から卵子が放出され、排卵が起こります。
排卵期には、急激なホルモン量の変動があるために、体調がすぐれないことがあります。また卵胞から膜を破って卵子が放出される際の物理的な痛みを感じることもあります。
黄体期
排卵が終わると、黄体期に入ります。黄体期は14日程度続いて、生理の初日になると卵胞期に戻ります。プロゲステロンの分泌量が増える影響により、「高温期」と呼ばれる時期になり、基礎体温が上がります。
プロゲステロンの分泌量が増えることで、子宮内膜が徐々に分厚くなり、受精卵が着床した場合に備えて準備を始めます。この期間に受精卵が着床しなければ、子宮内膜がはがれて生理が起こります。
ストレスを感じやすく、ダイエットも成功しづらい期間です。生活習慣を変えたり、使用している化粧品を変えたりするのは、控えておくとベターです。
生理不順や無月経の症状は?
生理不順や無月経の症状や、生理不順や無月経とみなされる基準を紹介しています。
生理不順や無月経を放置しておくと、生理不順や無月経の治療が長引く原因になったり、病気の発見が遅れたりする原因になります。生理不順や無月経が見られる場合は、早めに病院を受診しましょう。
生理不順
生理不順とは、正常な周期・期間から大きく外れて生理が起こることです。具体的にはこのような症状が挙げられます。
- 頻発月経(生理が頻繁にある)
- 稀発月経(生理が時々しかこない)
- 不正周期月経(生理がくる時期がバラバラ)
正常な生理周期は25日~38日程度、生理の期間は3~7日間と言われています。生理周期に個人差はありますが、ここで挙げた周期・期間から大きく外れている場合は、生理不順です。
無月経
妊娠していないにも関わらず、生理が3ヶ月以上こない状態を、無月経と呼びます。無月経も生理不順の一部に含まれます。無月経のまま放置すると、治療をしても月経がなかなか回復しなかったり、不妊の原因になることがあります。「生理がこないから楽になった」と思わずに、早めに治療しましょう。
無月経の場合は、以下のような理由が挙げられます。
- ストレスの多い生活
- 無理なダイエット
- 運動のしすぎ
- 太りすぎ
病院でのホルモン療法も有効ですが、生活環境を変えてストレスを減らしたり、無理なダイエットをやめたりなど、生活全般の見直しも必要です。太りすぎても痩せすぎても、無月経の原因となります。適度な体重を保ちましょう。
また、18歳以上にも関わらず一度も生理がない場合も、無月経とみなされます。17歳ごろになっても生理がこない場合は、病院の受診も視野に入れましょう。
思春期は生理周期がバラバラになりやすい
生理が始まったばかりの思春期は、生理周期がバラバラになりやすいです。これは、思春期はまだ性機能が十分に完成していないためであり、年齢を重ねればある程度生理周期が安定してきます。人によっては、初潮から生理周期が安定するまで10年程度かかることもあります。
思春期は、生理周期がバラバラになること以外にも、生理に関するお悩みが生じやすい時期です。生理痛がひどかったり、経血の量が多かったりなどのお悩みを抱えることがあります。
生活に支障をきたすほど症状がひどい場合や、不安がある場合は、一度医師の診察を受けましょう。病気でない場合が多いですが、「思春期特有のよくあるもの」と思いこんで放置したことにより、病気を見逃してしまう可能性もあります。
またストレスや無理なダイエットなどが原因になり、生理周期がバラバラになったり、生理が止まったりすることもあります。思春期は、受験や部活、人間関係などでストレスを感じやすい時期です。もし生理のお悩みがひどくなってきた場合は、我慢しすぎずに病院を受診することも検討してみましょう。
更年期や閉経が近づくと周期が変わる
更年期の時期になると、生理周期が短くなっていきます。これは、女性ホルモンであるエストロゲンが減少するために、脳下垂体から女性ホルモンの分泌を促すホルモンが多く分泌されるためです。その結果、卵巣が過剰に刺激されるため、生理周期が短くなります。
生理周期に加えて、経血の量にも変化が見られることが多いです。経血の量は、多くなる場合も少なくなる場合もあります。
更年期の時期は、女性ホルモンの分泌量が大きく変わるために、生理以外の面でも体調の変化を感じやすいです。このような変化を感じる方が多くいます。
- 頭痛・肩こり・腰痛などの痛み
- のぼせる
- 疲れやすい
- イライラしやすい
- 不眠
閉経が近づいてくると、逆に生理周期が長くなっていきます。2ヶ月、3ヶ月とだんだん長くなっていき、1年間生理がなければ閉経したと診断されます。日本人の平均的な閉経経齢は、50.5歳です。早い人は40代で閉経しますが、中には60歳が近づいても生理が続いている人もいます。
日常的に生理周期に気を配りましょう

生理周期は「自分の体調のバロメーター」になり、生理周期に気を配ることは、自分の体調を知るきっかけになります。変化があったときにすぐ気づけるように、日頃から自分の生理周期を把握しておくことが大事です。
また生理周期に変化があった場合は、「よくあること」と流さずに、病院を受診することも大切です。特に問題ない場合も多いですが、病気が原因となって生理周期が変動している場合もあります。病気を早期に発見するためにも、生理周期を把握しておきましょう。
女性にとって、生理は35~40年程度関わり続けるものです。自分の生理周期を把握して、毎日の生活に役立てましょう。
