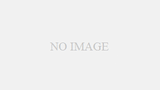中絶手術が必要になったら、準備することがたくさんありそうで、何から手をつけたら良いのかわからなくなりますよね。身近な人にも聞きづらいですし、どんどん不安が蓄積してしまう人もいるのではないでしょうか?
この記事では、未成年の方が中絶手術を受ける場合に知っておきたい、中絶できる期間やお金のことなどを解説しています。中絶手術を受ける際は、わからないことがたくさんあり不安な気持ちになりがちです。この記事をしっかり読んで、少しでも不安を解消しましょう。
中絶するに当たって知っておくべきこと4つ
まずは、中絶するにあたって知っておきたいことを4つ紹介します。中絶を決断するにあたって重要なことですのでしっかりと確認しておきましょう。
1.中絶できる時期は限られている
中絶ができる時期は法律で決められており、日本では妊娠21週6日までの中絶が可能です。胎児がお腹の外に出た後に、未熟児に対する医療を受けると生存できる時期になると、中絶ができないと定められてます。
中絶の際は、妊娠12週未満の中絶を「初期中絶」、妊娠12週〜妊娠21週6日までの中絶を「中期中絶」とよびます。初期中絶と中期中絶では、中絶の方法が大きく異なります。
妊娠12週以降の中期中絶は、初期中絶に比べて多額の費用が発生し、数日間の入院が必要になります。入院することで仕事や学校を必ず休む必要があり、周囲に中絶したことがバレやすくなります。中期中絶からは「人工死産」という扱いになるので、役所への死産届提出や火葬も必要です。
対して初期中絶は、中期中絶に比べて費用を抑えることができて、入院も必要ありません。役所への届出や火葬も必要ありません。
妊娠22週目以降は、法律により決められているので、どの病院でも中絶できません。また中期中絶は入院などの準備が病院側でも必要になるので、ギリギリのタイミングで病院へ駆け込んで中絶を希望しても、受け付けてもらえないことがあります。余裕を持たせて、どんなに遅くとも妊娠18週ごろまでには準備を始めましょう。
2.中絶のリスク
手術で子宮頸管を誤って傷つけてしまうなど、特別なことがない限り、今後の妊娠へのリスクはありません。
中絶の後は、子宮がもとの大きさに戻ろうとするために痛みを感じたり、出血が数日間続いたりすることがありますが、1週間程度で落ち着くことがほとんどです。
また、術後1週間程度は、感染症を起こすリスクがあります。1週間程度は入浴せずシャワーで済ませて、激しい運動は控えます。感染症予防のために飲み薬が処方されるので、忘れずに飲みましょう。
精神的なストレスでホルモンバランスが乱れて、体調不良になる可能性があります。特につわりやお腹がふくらむなどの体の変化がみられて、妊娠している実感が得られるようになるほど、精神的なストレスを抱えやすくなります。
3.費用
中絶の費用は、保険適用外になるため、病院によって異なります。目安としては、初期中絶が8〜15万円程度、中期中絶が30〜50万円程度です。中期中絶では、初期中絶よりも処置に時間がかかることや、入院が必要になる等の理由で、料金が高めに設定されています。都心部では、料金が高めに設定されていることが多いです。
また中期中絶では、病院に支払う費用以外にも、火葬や納骨などの費用が発生するので、総額としては50万円〜70万円程度必要です。中期中絶では、健康保険による出産育児一時金の対象になるので、病院に支払う費用の大半を一時金でまかなうことができます。
分割払いやクレジットカード払いが可能な病院もあるので、一度に支払うことが難しい場合は相談してみましょう。
4.手術に必要なもの
手術に必要なものは、各病院によって異なります。ここでは多くの病院で持参するように指示されるものを紹介します。
- ナプキン
手術後には出血が見られることがあるので、ナプキンの持参が必要です。妊娠週数により、昼用・夜用、持参枚数などを病院側から指定されることがあります。病院によっては、生理用ショーツの持参も求められることがあります。
- 健康保険証
中絶手術では健康保険が適用されませんが、その他の異常があった場合のために、念のため保険証を持参します。身元確認のために、保険証の持参を求める病院もあります。
- 同意書
同意書は、法律により提出が義務付けられています。中絶手術を受ける本人とパートナーの署名捺印が必要です。ただしパートナーと音信不通などの事情があり、パートナーの署名捺印が難しい場合は、病院で相談してみましょう。
中期中絶の場合は入院が必要なので、着替えや洗面具など、入院時に使用するものの準備も必要です。
ノーメイクでネイルもせずに来院するよう指示されることが多いです。ジェルネイルなど、サロンでのオフが必要なネイルをしている場合は、事前にサロンに行ってネイルをオフできるように、日程調整をしておきましょう。
よくある質問
未成年の方が中絶手術を受ける際に、気になる質問についてまとめました。各病院ごとに考え方が異なる部分もあるので、手術を受ける病院でも確認しておきましょう。
誰にもバレないように手術することは可能?
未成年が中絶手術を行う場合は、病院の方針により、親の同意が必要な場合が多いです。
母体保護法ではパートナーの同意書だけでOKと決められていますが、未成年を親の同意なしで手術するのにはリスクがあるため、同意書の記入が必要なことが多いです。またパートナーも未成年である場合は、パートナーの親の同意を必要としている病院もあります。
また初期中絶であっても、ある程度費用が高額になるので、親の協力を得ることをおすすめします。親に相談することが難しい場合は、兄弟でも構わないので、家族の誰かに相談してみましょう。
初診日、手術日ともに同伴者は不要であることが多いですが、万が一のために緊急連絡先の提出を求められることがあります。親やパートナーを緊急連絡先に指定する人が多いです。相手にも緊急連絡先に指定した旨を伝えておきましょう。初期中絶の場合は、手術当日に麻酔が切れてから帰宅するため、同伴者と一緒に帰宅できると安心です。
いつ手術をすると一番体に負担が少ない?
妊娠6〜7週ごろに中絶をすると、体への負担が少ないです。ただし妊娠に気がついた時点で、妊娠4〜5週目になっていることがほとんどです。妊娠6〜7週ごろに中絶をしたい場合は、早めに病院に行って相談をしましょう。
妊娠4〜5週目はまだ子宮頸管が硬く、手術時に子宮頸管を拡張することが難しいため、中絶には適していません。また子宮が小さいために、中絶手術後の残存物確認も難しいです。できるだけ早く中絶したいと希望していても、妊娠6〜7週ごろまで待つように指示されることがあります。
パートナーの同意を得たり費用を準備したりなど、中絶には準備が必要です。妊娠6〜7週ごろに中絶を行いたい場合は、妊娠に気づいてからなるべく早い段階で準備を始めましょう。
中絶手術をすると妊娠できなくなることはある?
中絶手術が問題なく成功すれば、その後の妊娠が難しくなることはありません。
しかし手術に失敗して、子宮内膜を傷つけてしまう可能性もゼロではありません。子宮内膜が一度薄くなりすぎると、その後の妊娠に差し支えることがあります。
中絶をくり返さないために
中絶後に生理が来るまで、1〜2ヶ月程度かかりますが、その間に妊娠することがあります。生理よりも前に排卵は起こっていますが、中絶手術後は排卵周期がわかりづらくなっているため、中絶手術後すぐに続けて妊娠することもあります。
中絶を繰り返さないためには、避妊をしっかりと行いましょう。低用量ピルを服用して避妊をすることをおすすめします。低用量ピルを毎日忘れずに飲み続けた場合、1年を通しての避妊率は99.7%です。他の避妊方法と比べて、非常に高い確率で避妊できます。
ただし、低用量ピルには性感染症を予防する効果はありません。性感染症の予防には、コンドームが効果的です。必ずコンドームも併用しましょう。低用量ピルとコンドームを併用すれば、避妊率もさらにアップして安心です。