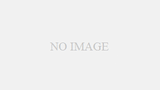「ピルにはどんなデメリットがあるのか知りたい」という方は多いでしょう。避妊だけでなく、生理のコントロールから生理痛やPMS(月経前症候群)、ニキビ、子宮内膜症の改善など、さまざまな効果で女性の生活の質を向上させてくれるピルですが、その一方でデメリットもあります。
ピルは毎日継続して飲む必要のある薬であるため、デメリットや副作用をしっかりと理解して、ピルに対する不安を払しょくした上で服用を続けることが大切です。
この記事ではピルのデメリットについて詳しく解説しています。安心して飲み続けるためにも、ピルのデメリットを正しく理解しておきましょう!
ピルの効果とは
ピルには、大きく分けて低用量ピルとアフターピル(緊急避妊薬)の2つがあります。
低用量ピルは排卵、子宮内膜の増殖を抑える作用があり、避妊目的のほか生理痛や排卵痛、PMS(月経前症候群)の改善に効果をもたらす薬です。
一方アフターピル(緊急避妊薬)はその名の通り、「中出しされてしまった」「コンドームが外れてしまった」など避妊に失敗した性交の後に緊急的に服用する避妊薬のことを指します。早く服用すればするほど高い避妊効果を得られ、性交から72時間(3日)以内であれば95%以上もの確率で妊娠を防ぐことが可能です。
今回は、避妊だけでなく生理時の不調や生理日のコントロールまでできる「低用量ピル」に焦点を当てて解説していきます。
アフターピル(緊急避妊薬)の効果や仕組み、注意点などについて詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。
ピルのデメリット
避妊の他にも多くの女性の悩みの種である、生理痛やPMSなど改善に効果がある低用量ピルですが、薬である以上どうしてもデメリットはあります。
低用量ピルは毎日継続して服用する薬であるため、メリットだけでなくデメリットについても詳しく理解しておきましょう。
毎日飲み続けなければいけない手間
低用量ピルは「毎日一錠ずつ」を「同じ時間」に飲み続ける必要があるため、手間がかかる点はデメリットといえるでしょう。低用量ピルには1シート21錠タイプと28錠タイプの2種類があり、錠剤を決められた順番に21日間もしくは28日間服用し、飲み終わったら7日間の休薬期間を設けるというサイクルを毎月繰り返します。
飲み忘れてしまうと日数によってはピルで得られる効果が薄れてしまう可能性があるため、ピルの服用を習慣として定着させることが大切です。
副作用が現れる場合がある
低用量ピルも薬である以上、副作用がついて回ります。低用量ピルの副作用として代表的な症状は、以下の通りです。
- 吐き気
- 嘔吐
- 頭痛
- 乳房の張り
これらの副作用はピルの服用を始めてから約1~2か月目に出ることが多いです。ただし人によって症状の程度はさまざまで、副作用が強く出る方もいれば全く出ないという方もいます。
低用量ピルのデメリットとして副作用を一番に挙げる方は多いかと思いますが、副作用として現れる不快症状のほとんどは体がピルの成分に慣れてくる服用から3か月のころには落ち着きます。
副作用が一過性のものであることを考えると、デメリットよりもメリットの方が格段に大きいといえます。
乳ガン、子宮頸ガンのリスクが上がる「かも」
低用量ピルと乳がん、子宮頸がんリスクについては、服用を続けることでわずかながら上昇する可能性があると考えられています。乳がんのリスクに関しては最近の36年のフォローアップ研究において、ピルを服用している女性の乳がんの発症率は1.08倍であったとの報告が上がっています。
しかし、一方でほかの何件かでは乳がん発症のリスク増加は認められなかったとの報告もあり、ピル服用による乳がんリスクはあくまでも「可能性がある」という範囲にとどまっているのが現状です。
参考:低用量経口避妊薬、低用量エストロゲン・プロゲストーゲン配合剤ガイドライン(案)
また子宮頸がんに関しては服用期間が長ければ長いほど、発症リスクが高くなる可能性があります。低用量ピルが子宮頸がんのリスクを高める要因として考えられているのは、以下の2つです。
- ピルを服用していると妊娠しないためコンドームをつけないで性行為を行う
- ピルに含まれるホルモンがヒトパピローマウィルスを活性化させている
このように子宮頸がんリスクに関してはピルに含まれる成分によるところもありますが、コンドームを使った避妊を行わないという二次的な要因も関係しています。
子宮頸がんは自分で予防できる病気なので、コンドームの使用を徹底することでリスク管理を行うことも大切です。子宮頸がんの発症リスクはピルの服用を中止すれば低下するもので、10年後にはピルを服用していない方と同等になります。
脳卒中や心筋梗塞のリスク
低用量ピルを服用していると血栓が発生しやすくなることから、脳卒中や心筋梗塞のリスクも乗じて高くなります。(血栓症リスクについては次項で詳しく解説します)
ピル服用による虚血性脳卒中(脳梗塞)、出血性脳卒中(脳出血)のリスク増加については、以下の通りです。
<虚血性脳卒中(脳梗塞)>
- 喫煙、高血圧のない女性:約1.5倍
- 高血圧のある女性:約3倍
- 喫煙習慣のある女性:約2~3倍
<出血性脳卒中(脳出血)>
- 35歳未満の非喫煙者で高血圧のない女性:リスク増加なし
- 高血圧のある女性:約10倍
- 喫煙習慣のある女性:約3倍
一方ピル服用による心筋梗塞のリスク増加については、以下の通りです。
- 喫煙、高血圧、糖尿病のない女性:リスク増加なし
- 高血圧のある女性:約3倍
- ヘビースモーカーの女性:約10倍
肥満や喫煙者、既往歴(病気にかかった経験)によっては上記の病気の発症リスクを高めてしまう可能性があるため、ピルの服用をおすすめしないケースがあります。
脳卒中や心筋梗塞などの病気に関しては医師に服用すべきか否かを判断してもらえるため、ピル服用の際には必ず相談するようにしましょう。
血栓症のリスク
血栓症はピルがもたらす最も重篤な副作用といえます。血栓症とは血液が固まって「栓」となり、血管内の血流を止めてしまうことでその先にある臓器の機能に障害を引き起こす病気のことです。
ピルの服用に抵抗を覚える最大の要因にもなっている血栓症ですが、実はピル服用による血栓症の発症率は年間1万人のうちの3~9人、死亡率にいたっては10万人に1人とごくわずかで確率は決して高くありません。
また血栓症を引き起こす可能性が最も高いのはピルの服用を始めてから1か月~3か月の間までで、それ以降は徐々に消失していきます。ただし以下の条件にあてはまる方は特に血栓症のリスクが高いため、ピルの服用を検討する際は必ず医師の指示を仰ぎましょう。
- 40歳以上の方(50歳以上の方に関してはピル服用は禁忌)
- 肥満の方(BMI25以上)
- 喫煙習慣のある方
- 片頭痛持ちの方(閃輝暗転など)
- 高血圧などの生活習慣病を抱えている方
- お酒を多く飲む方
毎月通院する手間や、費用がかかる
低用量ピルに興味はあっても、通院が面倒だったり費用面が気になったりして購入を躊躇しているという方は多いのではないでしょうか。低用量ピルは料金が高いイメージがありますが、1シート2,000円(税抜)から購入できる薬剤もあるためピル代が家計を圧迫することはありません。
また現在はオンライン診療の普及により、わざわざ来院することなく自宅にいながら医師の診察を受けることができるようになっています。ピルは最短翌日配送してもらえるため、すぐに服用を開始することが可能です。
オンライン診療なんて難しいんじゃない?パソコンもないし…と諦めるのはもったいありません。 スマホ一台あれば、オンライン診療は可能です。
スマホ用のピル処方専用アプリをインストールすることで、簡単に利用することができます。ピル処方の代金以外のお金が発生することもありません。アプリをインストールしたら、指示に従って問診を受け、あなたにぴったりのピルを処方してもらってください。
アプリ内でピルの飲み方や質問にも応えてくれ、アフターサービスも万全です。保険証も不要で利用できるのも嬉しいポイントです。少しでも興味があるなら、一度試してみることをオススメします。
意外と誤解されているデメリット
ピルのデメリットとして、「ピルを飲むと太る」「子供が出来にくくなる」「死亡率が上がる」といった情報を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。しかしこれらは間違いです。
誤った情報に翻弄されないよう、ピルに関する正しい知識を身に着けていきましょう。
ピルは飲んでも太らない
低用量ピルの服用によって脂肪が増えるということはありません。ただし数%の割合で、体重が1~2㎏ほど増える方がいます。これは、ピルが体内の水分量を増やすことによってむくみが生じているためです。
むくみによる体重増加は副作用が最も出やすい服用開始から3か月以内の時期に起こることが多いですが、ほかの副作用の症状と同様に1~2か月ほど経つと消失し自然と体重は落ちていきます。
「ピルが太る!」という誤った認識が浸透しているのは、1970年代にアメリカで発売されたピルの情報をいまだに引きづっていることが要因です。当時の低用量ピルは1錠あたりに含まれるホルモン量がかなり多く、むくみの症状を訴える方が相次いでいました。
しかし現在の低用量ピルは当時に比べホルモンの含有量が少なくなっているため、むくみを起こす確率はごくわずかです。実際、ピルを服用している女性で「ピルのせいで太ったからやめたい」という方はほどんどいないのが現状です。
子供ができにくくなることはない
低用量ピルの服用が原因で子供が出来にくくなることはありません。現に近年の研究によって、低用量ピルの服用を中止しても妊孕性(妊娠する力)への影響はないことが明らかになっています。
低用量ピルの服用を中止した後の、時期別に見る妊娠率の推移は以下の通りです。
| ピルの服用中止からの経過時期 | 妊娠率 |
| 1周期目 | 21.1% |
| 3周期目 | 45.7% |
| 1年後 | 79.4% |
| 2年後 | 88.3% |
上記の妊娠率はピルの服用経験がない女性の妊娠率と変わりません。また「ピルの服用期間が長いほど妊娠率を低下させる」という情報がありますが、これも間違い。
ピルの服用期間の長さによって妊娠率に差が出ることはありません。ただし上記の表からもわかるように、ピルの服用を中止してすぐのころはホルモンバランスが戻っていないため妊娠率は低くなります。
ピル中止から大体2~3か月程度で体のホルモンバランスが整うため、以降はピルの服用前と同様に自然妊娠が可能です。
死亡増加率は変わらない
2013年にピル服用による死亡例が新聞で取り上げられて以降、ピルの副作用である血栓症に起因する死亡増加率に注目が集まっています。しかし前項の血栓症リスクの項でもご紹介した通り、血栓症による死亡率は10万人に1人と非常に低い水準です。
また心筋梗塞などの心血管系疾患による死亡も極めて少なく、ピルの服用が死亡増加率に与える影響はほとんどありません。前述の通りピルには血栓症や子宮頸がん、乳がんの発症リスクを高めるとされていますが、全体の死亡率で見ると低用量ピルを服用している女性の方がピルを服用していない女性よりも死亡率が低いことが分かっています。
5年未満の服用なら子宮頸ガンのリスクは上がらない
低用量ピルは子宮頸がんのリスクを高めるとされていますが、これは5年以上の長期服用の場合です。ピルの服用歴が5年を超えてくると子宮頸がんの発症リスクが徐々に高まり、10年後には2倍に達するといわれています。
一方5年未満の服用であれば、子宮頸がんの発症リスクはごくわずかです。これまでの研究により、子宮頸がんの原因はヒトパピローマウィルスによる性感染症であることが明らかになっています。
コンドームをつけないで性行為を行うと直接内膜に体液が付着してしまいウィルスに感染する可能性を高めてしまいますが、コンドームを使用することでこのリスクは下げることができます。
子宮頸がんは予防と検査によって発症リスクを限りなく下げることができるため、ピルの服用歴に関わらずコンドームの使用と定期的な検査を受けることが大切です。
ピルはリスクよりもメリットの方が多い!
この記事では、ピルのデメリットについて解説しました。
ピルには副作用や血栓症リスクなどのデメリットがありますが、一方で避妊や生理時の不快症状の緩和といった大きなメリットがあります。またピルの服用によって、治癒率の低い卵巣がんや子宮体がんの発症リスクを大幅に下げることが可能です。
長年悩まされていた、ひどい生理痛から解放された方がたくさんいます。
避妊のために飲むというイメージが強いピルですが、実は、それ以上に多くのメリットがある薬です。生理痛やPMSで苦しんでいる期間が軽減されたり、自主的に避妊ができたら、女性はもっと自由に生きられるはずです。
婦人科でピルを処方してもらうのが恥ずかしいと思っていた方でも、最近はオンライン診療を使って簡単にピルを入手することができるようになりました。
低用量ピルは20代~40代が選ぶ、人気ピル処方に選ばれるだけあって、アフターサービスも万全。簡単に長く使える便利なピル処方アプリです。
これからピルを使って人生を改善していきたい方は、ぜひこのアプリから試してみるのが良いでしょう。